数学的な 何やら わけわからん内容と 君の頭の中で ごっちゃになってるんだね わたし
かぜ
なってみると辛い でも なるまで忘れてる 恋煩いと 同じ
いい加減
時間は限りあるもので 個人の持っている時間は確実に減っていく 常に意識しているほど 無意味なこともないけれど たまにはどうしても 思ってみなければならなくなる 《何をしている 時間は過ぎるぞ》 それは 自分の過去が 証明してくれただけでも十分なのに 現在という 唯一コントロールが及ぶはずのものまでが ある時すまして その事実を突きつけたりもする 《何をしている 時間は過ぎるぞ》 もういい とっくのとうにわかっている なんにしろ やるだけやってみるより他に ないんじゃないか たいがい行き当たるのは そんな程度の いい加減
手紙
純粋な少女のくれた手紙を 古いノートの間に見つけた 私の書いた小さな詩を とても素敵だと言ってくれたのだ ためらいがないどころか あんまり素直に心を打ち明けていて 私はなんだか今にも 優しい気持ちを誘われてしまう あの娘が どんな気持ちで手紙をくれたのかは あの時にだって分かっていた どんな気持ちで暮らしていたのかを 悲しいくらい私は知っていた 私の手元には 少女の純粋が今も残って 一つの勇気を与えてくれている あの娘の手元にも 私の書いた詩が まだ あるのだろうかしら
詩
心を 切り刻んで 細かく 切り刻んで ある時ふと 紙ふぶきのように それを一斉に 空(くう)に舞わせたところに それは生まれたのだろう 純粋な魂を 粉々に 切り刻んで 紙ふぶきのように 散らせたなら それはきらきらと 瞬間の輝きを放ちながら 切り刻まれた永遠となって 静かに降り積もっていくわけだ
壊れた独楽
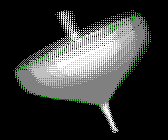
壊 れ た独楽でもそれなりに回る なんだか自分が回っている ようでこんなものさえ 捨てられない で い る

雫(しずく)
旧道のトンネルの中は
いつも暗く
ひんやりとしている
まるで永遠のような
その静寂の中を
ひときわ冷たい水の
雫の落ちる音が
響くとき
響くとき
少しだけ
時間の流れがひずんで
後戻りするんだが
後戻りするんだが
みみずの死
どくだみの花が咲く 初夏のベッドで 僕は気ままに生きていた そこが 僕の全ての生涯の在り処 それでよく それでしかなく 土の臭いはそのまんま僕の 生と死を抱く 優しい場所であったのだ どこに行こうという望みも ありはしないし 今までだって持ちはしなかった 十分な安穏に 時たま寝返りを打つことくらいが 僕の仕事で そのままいることにだけ 僕の生活は終始するはず それでよかった 遠くで かあかあかあかあ かあかあかあかあ 鳴く鳥も 僕は一度も見たことはないが それはそれで 別にどうでもいいことだった あたたかい 黒い土に 僕は愛されていると思っていたからだ 愛していたからだったろう そうだったろうと思うのだ なのに 突然だ 僕は子供の持つ棒きれにひっかけられ 落とされてはまたひっかけられ かたくて熱く焼けた日向のコンクリートの上に運ばれ のた打ちまわり あえぎ 見たこともないその場所でいたぶられ 孤独の中で絶望し ひからびていく自分を どうすることも できないまんまひからびていった 見たこともない光という光が 青い色のどんどん濃くなっていく空が 僕の目には映っていた 僕はその時ふと ああ これが死というものなのかと はじめてわかった
夏
明るい蜃気楼がそっと遠のき ふと我に返ると 人々はその傍らに ほこりと蜘蛛の巣とかびの領分と化した 古臭いあばら屋を見出だすであろう まもなく それが自らの帰るべき住み処であったことを どこか見覚えのある調度から認めねばならないであろう 同時にそうすることの空しさをわかりながら きっと呟くであろう 《まさか こんな はずでは》 人々はそして もしや長い長い魔法にかかっていたのかしらと やっとのことで思い至るであろう だれかにささやかれた 忌まわしいまじないの言葉が そう言えば と思われてくるであろう やがて柔らかな愁いが 心の中にはびこって 無数の蜘蛛の巣のように きれいに幾何学模様を作っているのを もはや諦めた顔つきで ぼんやりと眺めるであろう もちろんそれは これまでの時間を鮮やかに記念して 静かにきらきらとか細く揺れて 静かな光を放ち続けるであろう
人生
へたをすると 馬鹿馬鹿しい芝居にだって 心の底から笑うようになる 心の底から泣くようになる あるいは どちらもできなくなる