時間は限りあるもので 個人の持っている時間は確実に減っていく 常に意識しているほど 無意味なこともないけれど たまにはどうしても 思ってみなければならなくなる 《何をしている 時間は過ぎるぞ》 それは 自分の過去が 証明してくれただけでも十分なのに 現在という 唯一コントロールが及ぶはずのものまでが ある時すまして その事実を突きつけたりもする 《何をしている 時間は過ぎるぞ》 もういい とっくのとうにわかっている なんにしろ やるだけやってみるより他に ないんじゃないか たいがい行き当たるのは そんな程度の いい加減
長い列
「これは どなたの お葬式 ですか」 凍りつく吐息の向こうに 天は無意味なほど明るく 透き通っていた 「ほら あの方の」 持ってきて そこに置いたばかりの ちんけな水車が さっき通りすぎてきた 入り口のところで ちょろちょろと水を受けて 回っていたが 「どなたの お葬式 ですか」 「ほら あの方の」 受付の世話で 淡々と働いているあの方の どんなゆかりの 葬儀だというのだろうか 僕は考えながら そのまま列に運ばれ 立ち止まっては また一歩 思い出したように 進んで行った 「どなたの お葬式 ですか」 「ほら あの方の」 あれは 葬儀屋の人ではないのだろうか 手慣れた様子で あれこれと ことを仕切っているとも見えるのだが 考えあぐねて振り返ると 僕の後ろにも 果てしない列ができていた 「どなたの お葬式ですか」 踏みしだかれた落ち葉が 僕の足下に乱れている だれの葬儀なのか 僕には依然 わからなかった それなのに 列に運ばれているうちに 僕はいつしか やり切れない悲しみの中に なぜか沈み込んで どうすることも できなくなっていた もうどうでもいい どうでも いいのだ 「ほら あの方の」 泣きそうになるのを どうやら堪えて 僕はおもむろに 答えてやった そうしてただ また一歩 動いてゆれる 長い列
ポセイドン
夏は夕暮れ 透明なほど 肌の白い女が また頬を涙に濡らして 海辺に立った ゆりかごの 調べはカノン たれか知る 涙のゆくへ 風の伝ふる 静けきメルヘン 女は 遠くを見つめたまま 固く唇を 結びなおした それから なおもずっと 涙は流れ続けた ゆりかごに 時はまどろむ 小波の 寄せつ返しつ 彼方なる ノスタルジーの ポセイドンは 女に恋していた 切ないため息は 今日までに 幾度となく繰り返されていた けれども女は そのことに 永遠に気づきはしない それは風の音と ほとんど同じに すぎなかったのだから
ガラス窓
そこにはひとつの
ガラス窓があって
向こうに景色が開けている
あこがれていた景色は
ずっとあの頃の通り
色褪せない
うす暗がりから望む
景色の明るさは
永遠をたたえて無垢なままだ
窓のガラスには
うっすらと僕が映り
あこがれたまま
立ち尽くす姿も
ずっとあの頃の通り
変わらない
ガラス窓から
外の景色を眺めるうち
知らず知らず
そこに映る自分自身を見つめて
絶望しそうになっていることが
僕にはよくある
「まだまだだ」
その言葉が
二つの意味で
葛藤する
ガラス窓は
なぜか汚れやすくて
きれいに拭ってやらないと
すぐに景色が見えにくくなる
あんまり度々
こすって磨いているせいで
ガラス窓には
骨董品じみた細かな傷が
無数にできてしまっている
ガラス窓がやがて
手に負えないくらい
傷だらけとなり
僕の姿を
少しも映し出さなくなった頃
あこがれていた景色は
いよいよ僕からは
見えないものになるのだろうか
黄色の光
看板が斜めになり くすんだペイントの中にある黄色の 妙に鮮やかな光を放っているのが 実は君であるということを 僕はとうとう告げることなしに 今日まで時間を終えてきてしまった そうしてブリキの看板を きちんと立て直す術も持たず それでも黄色い光のところから 目を離せないまま ぼんやり見守り続け ほうりゃとばかりに 時たま思い出して自分の ずいぶんと色あせた情熱のかけらをちぎっては ばおんと看板にぶつけてみるのだ 心なしか 看板がまた斜めになる 光は一層鮮やかだが
大砲
ずどんと大砲が鳴ったあとの 僕の心の中を支配する余韻が しつっこくてやりきれない 頭痛のガンガンする痛みには もうあきらめもあるが しかし 僕の心の中を埋め尽くすもの 大砲の余韻が鳴り止まないのだ 大砲は僕の上にある未来をめがけて そこには多少のデフォルメもあろうが 図太くて鈍い音とともに 天高く打ち上げられたのだ それなのに まだ砲丸は落ちて来ない 落ちて来ないが 空砲などではあり得ないはず 確かに それは僕が打ち上げたのだ いつもいつも ずどんと大砲が鳴ったばかりで 余韻が鳴り止まないまま 砲丸もまだ落ちては来ない
秋
紅葉を待ち受ける木梢 仕事は終わりに近づいたとささやく木梢 天が澄んで懐かしいほどに ふと昔の夢が微笑みとなって うっかり口をつく僕の口癖 「これが潮時……」 冴えた空気と穏やかな陽光 コンチェルトみたいに戯れ合い それはそれは静かに流れる しかしね おまえたち そろそろ覚悟を決めておこうよな これからの風は いよいよ冷たくなっていく はじめから 決まりきってるんじゃないか
音
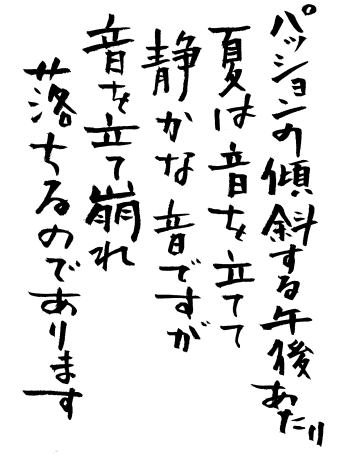
パッションの傾斜する午後あたり
夏は音を立てて
静かな音ですが
音を立て崩れ落ちるのであります
ある朝に
僕の生み出せるものは うんちくらいのものだ いつになく 頑張ってみたところで 出来てきた作物はといえば いつも同じにひょいとあり そうして 勢いのある水なんぞに流されて どこかへ溶けて消えちまう 僕にしてみたところでもう 金の卵は生めないことを知っているから いちいちがっかりもしないけれど 時々考えてみたりする こんなものにしても 喜んで受け容れる畑のひとつ どこにかあるんじゃないかしらんと そうでなけりゃ 僕だって鼻を つまみたくさえなっちまう