ずどんと大砲が鳴ったあとの 僕の心の中を支配する余韻が しつっこくてやりきれない 頭痛のガンガンする痛みには もうあきらめもあるが しかし 僕の心の中を埋め尽くすもの 大砲の余韻が鳴り止まないのだ 大砲は僕の上にある未来をめがけて そこには多少のデフォルメもあろうが 図太くて鈍い音とともに 天高く打ち上げられたのだ それなのに まだ砲丸は落ちて来ない 落ちて来ないが 空砲などではあり得ないはず 確かに それは僕が打ち上げたのだ いつもいつも ずどんと大砲が鳴ったばかりで 余韻が鳴り止まないまま 砲丸もまだ落ちては来ない
昼下がり
平和な海の掟に 松の梢はうっとり酔い ほうっと明るんだ空が 妖怪を称えあげて光り ジュネーブに飛んだ姉の 手首にはブレスレット 細いブレスレット 鎖につながれた 奴隷の憂い 静かな 海の憂い らっきょうが ガリリと音を残す そういう夏の昼下がり
煙
雨の中を 上昇ってゆく煙が あんまりにも白くて 僕は 「見えること」と「見えないこと」との 価値の相違なんぞを考えている 見えている白さが 無限に 宇宙にまで 届くのではないのを 不思議なことのように思い詰めている 「正直」というものと それに反するものとの違いかと考えてみる 実は「成長」という一言で 説明し尽くされるものかとも考えてみる 少しくらいは 幸福と不幸との差があるのかもしれないと考えてみる 実体と虚体という違いではないことだけは確信している そうしているうちに 白さが見えなくなったその時 煙でなくなるのだということに 不可解さえ感じ始める そうして それが世界を包むことに思い至り 雨の降ってくるわけが 知れる気がした
富士山
富士山には 随分たくさんの思い出がある 僕が富士山を好きなのは 数々の思い出の中に どっしりと富士山が座っている その偶然のためなのだろうか なかでも とりわけ強く僕を揺り動かす 八年前の二人の在り方と その背景にあるどでかい富士山 僕を押しつぶそうとする
水辺で
源五郎の棲む池のほとりを 小さな竜巻(つむじかぜ)が訪れたとき 葦たちは穂先をなびかせて歌った 理不尽であればあるほど 風は期待を 唆(そそのか)すもので いわば竜巻などは 葦たちには夢みたいなものなのだ 葦たちの騒ぎ様ときたら尋常ではない 我こそはと一斉に歌い出すのだ 小さな竜巻にとりすがるように踊るのだ よほど思い詰めていたのだろうか 水辺に棲むことに あるいは倦んでいたのだろうか この時とばかりに 狂ったかのように 源五郎はあきれて見ていたが まもなく 「阿呆らしい」 と 小さな声を投げ出し すうい と 泳ぎ始めた そんな折だ 葦というのは本来 それぐらいの竜巻で抜け飛ぶようなものではないらしいのだが 一本の葦が飛んだ その小さな竜巻が巻き上げたのだ だれもが「ああ」という微かな声を漏らした 同時に風は去り 辺りは静かになった 竜巻と一緒に舞い飛んだ葦も どこかへ消えた 池の水面がまだ激しく波立っていて 源五郎は泳ぎにくいのにうんざりしたけれど やがて生涯を愛するかのように 「面白い」 と 一言呟く
秋
紅葉を待ち受ける木梢 仕事は終わりに近づいたとささやく木梢 天が澄んで懐かしいほどに ふと昔の夢が微笑みとなって うっかり口をつく僕の口癖 「これが潮時……」 冴えた空気と穏やかな陽光 コンチェルトみたいに戯れ合い それはそれは静かに流れる しかしね おまえたち そろそろ覚悟を決めておこうよな これからの風は いよいよ冷たくなっていく はじめから 決まりきってるんじゃないか
馬鹿
夢を追いかける人のきららかな表情を すっかり信じて微笑する 僕は馬鹿だよ ひたむきに行う人の 明るい顔を見ていると 悲しむべき僕の感情がついにはなくなり 嬉しいばかりの僕が出来上がって 得意になる 僕は馬鹿だよ 《「純粋」などあるわけないさ》 そうだろうか そりゃあ僕にも分かっている(分かっていない?) 分かってはいても もっと何かありそうに思われて 諦めきれないでいる 僕は馬鹿だよ 馬鹿でもいい なんて開き直る 僕は馬鹿だよ
人生
へたをすると 馬鹿馬鹿しい芝居にだって 心の底から笑うようになる 心の底から泣くようになる あるいは どちらもできなくなる
理想
求めることをやめてしまえば 味気ない四拍子に暮らし ついと思い詰めてしまいそうで 周りの人たちを眺めながら 人生の意義などを考え直しては やっぱり理想を求めるに限ると 結論するのである
独り
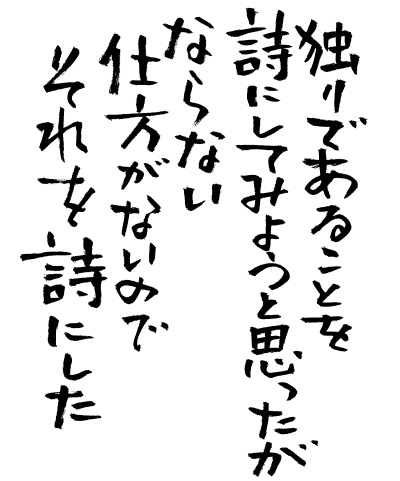
独りであることを 詩にしてみようと思ったが ならない 仕方がないので それを詩にした