眠気によっても 僕の宇宙への思いは何も 何ひとつも変わらず深刻なのだ 間もなく意識は薄れながら 今日の雑多ながらくたを遥か 向こうの山陰に埋め葬ろうとしている そうして僕の世界はまぶたの中で ようやく色彩を取り戻し始め 最大級の意味を与えられるはずなのだ それなのにどうだ やっぱり駄目だ 僕の宇宙への思いは何も 何ひとつも変わらず深刻なのだ がらくたどもが あるいは 存在を主張するその叫びか 地鳴りが止まない 地鳴りが止まない 地鳴りが止まない そのせいなのだ
黄色の光
看板が斜めになり くすんだペイントの中にある黄色の 妙に鮮やかな光を放っているのが 実は君であるということを 僕はとうとう告げることなしに 今日まで時間を終えてきてしまった そうしてブリキの看板を きちんと立て直す術も持たず それでも黄色い光のところから 目を離せないまま ぼんやり見守り続け ほうりゃとばかりに 時たま思い出して自分の ずいぶんと色あせた情熱のかけらをちぎっては ばおんと看板にぶつけてみるのだ 心なしか 看板がまた斜めになる 光は一層鮮やかだが
晩夏
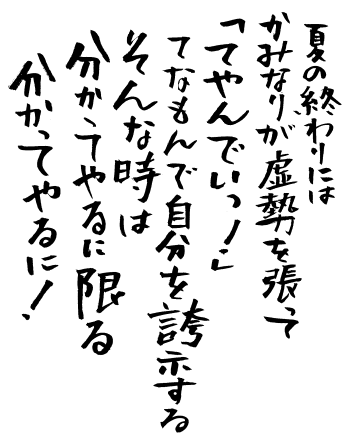
夏の終わりには かみなりが虚勢を張って 「てやんでいっ!」 てなもんで自分を誇示する そんな時は 分かってやるに限る 分かってやるに!
夏
明るい蜃気楼がそっと遠のき ふと我に返ると 人々はその傍らに ほこりと蜘蛛の巣とかびの領分と化した 古臭いあばら屋を見出だすであろう まもなく それが自らの帰るべき住み処であったことを どこか見覚えのある調度から認めねばならないであろう 同時にそうすることの空しさをわかりながら きっと呟くであろう 《まさか こんな はずでは》 人々はそして もしや長い長い魔法にかかっていたのかしらと やっとのことで思い至るであろう だれかにささやかれた 忌まわしいまじないの言葉が そう言えば と思われてくるであろう やがて柔らかな愁いが 心の中にはびこって 無数の蜘蛛の巣のように きれいに幾何学模様を作っているのを もはや諦めた顔つきで ぼんやりと眺めるであろう もちろんそれは これまでの時間を鮮やかに記念して 静かにきらきらとか細く揺れて 静かな光を放ち続けるであろう
亡命
彼の瞳に映る世界は
未来へと確かに漸進しているはずなのだ
ファシズムに立ち向かう
彼の精神は恐ろしく崇高いではないか
亡命を決意するまでの過程を今
つぶさに振り返ろうとも
その叫びも沈黙も捧げた自己犠牲も
全ては正義への願いに裏付けられていた
〈だからこそ余計 彼はその瞑眩に
自らの全体さえ見えなくなるのだ〉
もちろん
彼は失うことを選んだ者だ
愛すべき祖国を
愛すべき人々を
自らの国籍を
全てを
理想を希求する在り方までも
失わねばならなかったのだ
こうするより他に
彼の生きられる方法はなかったのだ
〈体制に反旗を翻した者は時に
信ずる正義のために死を選び
殺されることをも誇りにする〉
しかし
彼は生きたかったのだ
自分を生かそうと思ったのだ
犬死にではならなかったのだ
彼は理想を守りたかったのだ
彼の死はそのまま彼の
孤高なる精神の消滅を意味する
それだけは
彼には耐えがたいことだったのだ
あってはならないことだったのだ
〈そして 彼は 亡命した〉
だがすぐに彼は
その皮肉を思い知らねばならない
たとえファシズムに染まり切っていても
それは彼の祖国であった
たとえファシズムを信奉する者でも
それは彼の同胞たちであったのだ
憎むものも
愛するものも
彼には一つしかなかったのだ
〈亡命より他に 選ぶべき道は なかったではないか〉
そう呟く刹那
彼はまた
自分を苛み始める
〈たとえ 殺されようとも どうして
最後まで 抗い通さなかったのか〉
時間も空間も
もはや彼の味方ではない
彼はかたく歯をくいしばり
じっと思い詰めるだけだ
彼の苦悩が
愚かな失敗によるものではなく
譲れない成功の結果だからだ
仕事
雨のようなもので
どっちみちなるようにしかならないのだが
てるてる坊主を作ったり
雨乞いの神事をしたり
ずいぶん熱心にやってみたりするのだから
それも大真面目で
やってらんないくらい胸が痛むんだ
自分の仕事の意義を
何とか見つけ出さないじゃいられなくて
人間てけなげだ
俺らもけなげだ
けなげだけれど
やってらんないくらい胸が痛むんだ
しろつめ草
校庭の片隅で見つけた
幸運の小さな象徴(しるし)
「ほら 四葉のクローバだよ」
「クローバ? 四葉の? ほんとだ!」
「あげるよ」
「わあ ありがとう」
初夏の
うららかな昼休みは
清々するくらい
明るくて綺麗だ
明るくて綺麗な昼休みであっても
そう単純にゆくことばかりではない
「ほら 四葉のクローバだよ」
「先生はそんなことやって楽しいんですか?」
なんて言いやがる奴だっている
そりゃあないんじゃないか
と思いながら
「四葉のクローバ 幸運の象徴だよ」 /しるし
と胸のポケットに無理やり挿し入れてやる
そうしたら
あきれたみたいな顔して見ていやがる
しろつめ草はポカポカした太陽をたくさん
浴びて育っているんだから負けない
だるまと車掌
奴の現在の在り方を、例えば「忘れられただるまさん」と言うことができる。人々の幸せを祈りながら、ただじっと、手も足も出せないまま黙っていることより、仕事はない。その上、いつの間にかだれもがその存在を忘れている、いつまでも両目を入れてもらえない、そういうだるまさんが、よくある、それだ。
また、例えば「ワンマンバスの車掌」とも見ることができる。既に役割は無くなっている、今の状況を分かりながらも、お客さんとは違うだけの気持ちを持っているのだから、質がよくない。結局のところ、お客さんと同じように座って、終点までバスに揺られるよりない。もう、役割は既に終わっているのだ。お客さんならば、目的地に着くためにバスに乗っているわけで、それでいいと言えるんだが、目的とすることを何もしないまま終点に降り立った車掌は、ようやく、自分の存在価値を、考え始める。
いつの時代も、時の流れとともに、必然的に不要のものとなり、歴史の彼方へと、忘却の彼方へと、いつの間にか遠ざかるものがある。そういうとき、ほとんどのものはひどくさりげなく、消え、あまりに静かだ。それが引き際の理想、だから、達人のように、奴もそういう風にやってみたかったが、そこまで自然にはなれなかった。どんどん廃れる自分を、そこまであきらめきれない、奴は達人にはなれなかった。
そうして、ほこりを被っただるまさんは、というと、ついに旅に出る、決心をした。一方、不器用な車掌さんは、というと、ついに転職の、決心をした。ちょっとばかり、遅すぎる決心ではあるのだが。
考えてみりゃ、滑稽な話、それでおしまい。
ゆりかご
ゆりかごに揺られながら 僕はうっとりとしている 君の指の白さを眺めて どうしてあんなものが 自然によって生まれてくるのだろうなどと 呑気に思っている間 僕の中には 君の不思議がたくさんみなぎって 僕を満たすのだ ゆりかごは宇宙の 愛らしい償いである だから優しく僕を揺らし うっとりと僕をなぐさめる はらはらしながら ゆりかごの結末を予感しつつ 僕はただ うっとりとしている
御坂峠
開けた景色が見たくなって BMWで御坂峠に行った 学生時代 太宰さんのいしぶみを訪ねた 富士山と河口湖の 大きな景観 真っ暗なトンネルの手前 なんだか淋しいような気になる あの 御坂峠 「月見草」の碑の前に立ったら 二十歳の頃に愛した人を どうして失ったのかと ついといたたまれなくなって 天下茶屋の山菜そばを喰い 元気になったようなつもりで 帰ってきたが