そこにはひとつの
ガラス窓があって
向こうに景色が開けている
あこがれていた景色は
ずっとあの頃の通り
色褪せない
うす暗がりから望む
景色の明るさは
永遠をたたえて無垢なままだ
窓のガラスには
うっすらと僕が映り
あこがれたまま
立ち尽くす姿も
ずっとあの頃の通り
変わらない
ガラス窓から
外の景色を眺めるうち
知らず知らず
そこに映る自分自身を見つめて
絶望しそうになっていることが
僕にはよくある
「まだまだだ」
その言葉が
二つの意味で
葛藤する
ガラス窓は
なぜか汚れやすくて
きれいに拭ってやらないと
すぐに景色が見えにくくなる
あんまり度々
こすって磨いているせいで
ガラス窓には
骨董品じみた細かな傷が
無数にできてしまっている
ガラス窓がやがて
手に負えないくらい
傷だらけとなり
僕の姿を
少しも映し出さなくなった頃
あこがれていた景色は
いよいよ僕からは
見えないものになるのだろうか
宛名書き
年賀状の宛名書きを パソコンで手伝ってやるのは ここ数年の私の習い 昨年の住所録を印刷して 母に渡してやると 一年前に頂いたお賀状の束と ひとしきり時間をかけて 照らし合わせている しばらくすると 私の部屋にやって来て 出す人とそうでない人 小さな印でよりわけた住所録を 遠慮がちに私に差し出す 私が受け取ろうとのぞき込むと 「この先生、死んじゃった いい先生だったのに」 指先で一つの名を押さえてつぶやくと 母は急に涙ぐんで それなり逃げるように 背中を丸めて部屋を出ていく 乙女なりし母の 涙をすすりあげる声が なおも静かに聞こえつづける
たぶん
世界中に毎日 絶滅している生物が たくさんあると聞くが その終わりはきっと 人知れず あっけないものなのだろう 終わってみれば 結構あっけないものなのだろう 終わったんだか 何だか よく分からないような ささいな 出来事なのだろう 亜熱帯の森林が伐採され 地球のオゾン層が破壊され 物言わぬ海に 最後のツケは回され 人間の横暴を責めてみるのも 何だか絶望的に思われるばかり 今さら原因が何かと 問い直してみたところで たいした手だては見つからない みんな 自分のことだけで 精一杯なのだから 「たぶん それでいいんだよねえ」 そんなふうに 大概のものは 結構あっけなく終わるものなのだから 人の人生が 終わるときであっても そしてたぶん 人の歴史が 終わるときであっても 「たぶん それでいいんだよねえ」 いいわけないじゃないか! と だれでも口を揃えて言いはするだろうが
霙(みぞれ)
霙の中を 卒園式帰りの母子が 傘をさして通り過ぎます 着飾った若いお母さんは 子供の制服の胸にあるリボンと ちょうど同じようなピンクの きれいなスーツを着ているのです 冷たい霙は 傘の上にもうっすら積もって 子供の黄色い傘には ちょっと重たそうに思われるのですが どうやらへっちゃらみたいに ぜんぜんお構いなしに 子供は飛び回って歩くのです 茶色い雨傘の中で それを微笑ましく眺めながら だれが立ち止まってみても 何者も気付きはしない! そういう春の昼下がり 冷たい霙は 一向に降り止みません 冷たい霙は 私の上にも積もっているのかと そうやって思い至ってみると それは何だか結構うっとうしく やけに重たく 道端でふと 何だか泣きたいような気分になって けれどまた もう一度歩きだすより他に 私にはなかったのです
地鳴り
眠気によっても 僕の宇宙への思いは何も 何ひとつも変わらず深刻なのだ 間もなく意識は薄れながら 今日の雑多ながらくたを遥か 向こうの山陰に埋め葬ろうとしている そうして僕の世界はまぶたの中で ようやく色彩を取り戻し始め 最大級の意味を与えられるはずなのだ それなのにどうだ やっぱり駄目だ 僕の宇宙への思いは何も 何ひとつも変わらず深刻なのだ がらくたどもが あるいは 存在を主張するその叫びか 地鳴りが止まない 地鳴りが止まない 地鳴りが止まない そのせいなのだ
夏
明るい蜃気楼がそっと遠のき ふと我に返ると 人々はその傍らに ほこりと蜘蛛の巣とかびの領分と化した 古臭いあばら屋を見出だすであろう まもなく それが自らの帰るべき住み処であったことを どこか見覚えのある調度から認めねばならないであろう 同時にそうすることの空しさをわかりながら きっと呟くであろう 《まさか こんな はずでは》 人々はそして もしや長い長い魔法にかかっていたのかしらと やっとのことで思い至るであろう だれかにささやかれた 忌まわしいまじないの言葉が そう言えば と思われてくるであろう やがて柔らかな愁いが 心の中にはびこって 無数の蜘蛛の巣のように きれいに幾何学模様を作っているのを もはや諦めた顔つきで ぼんやりと眺めるであろう もちろんそれは これまでの時間を鮮やかに記念して 静かにきらきらとか細く揺れて 静かな光を放ち続けるであろう
富士山
富士山には 随分たくさんの思い出がある 僕が富士山を好きなのは 数々の思い出の中に どっしりと富士山が座っている その偶然のためなのだろうか なかでも とりわけ強く僕を揺り動かす 八年前の二人の在り方と その背景にあるどでかい富士山 僕を押しつぶそうとする
水辺で
源五郎の棲む池のほとりを 小さな竜巻(つむじかぜ)が訪れたとき 葦たちは穂先をなびかせて歌った 理不尽であればあるほど 風は期待を 唆(そそのか)すもので いわば竜巻などは 葦たちには夢みたいなものなのだ 葦たちの騒ぎ様ときたら尋常ではない 我こそはと一斉に歌い出すのだ 小さな竜巻にとりすがるように踊るのだ よほど思い詰めていたのだろうか 水辺に棲むことに あるいは倦んでいたのだろうか この時とばかりに 狂ったかのように 源五郎はあきれて見ていたが まもなく 「阿呆らしい」 と 小さな声を投げ出し すうい と 泳ぎ始めた そんな折だ 葦というのは本来 それぐらいの竜巻で抜け飛ぶようなものではないらしいのだが 一本の葦が飛んだ その小さな竜巻が巻き上げたのだ だれもが「ああ」という微かな声を漏らした 同時に風は去り 辺りは静かになった 竜巻と一緒に舞い飛んだ葦も どこかへ消えた 池の水面がまだ激しく波立っていて 源五郎は泳ぎにくいのにうんざりしたけれど やがて生涯を愛するかのように 「面白い」 と 一言呟く
独り
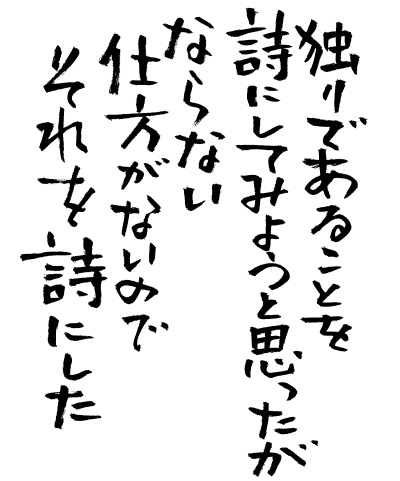
独りであることを 詩にしてみようと思ったが ならない 仕方がないので それを詩にした
弱音を吐くが
たくさんの裏切りに ちょっとばかり疲れてしまったよ ちょっとばかりいけないよ ずいぶんと 裏切られることにも慣れてきたとは 思うのだがまだまだ やっぱり悲しいというのか やり切れないじゃないかよ やってらんないくらい寂しいよ