そこにはひとつの
ガラス窓があって
向こうに景色が開けている
あこがれていた景色は
ずっとあの頃の通り
色褪せない
うす暗がりから望む
景色の明るさは
永遠をたたえて無垢なままだ
窓のガラスには
うっすらと僕が映り
あこがれたまま
立ち尽くす姿も
ずっとあの頃の通り
変わらない
ガラス窓から
外の景色を眺めるうち
知らず知らず
そこに映る自分自身を見つめて
絶望しそうになっていることが
僕にはよくある
「まだまだだ」
その言葉が
二つの意味で
葛藤する
ガラス窓は
なぜか汚れやすくて
きれいに拭ってやらないと
すぐに景色が見えにくくなる
あんまり度々
こすって磨いているせいで
ガラス窓には
骨董品じみた細かな傷が
無数にできてしまっている
ガラス窓がやがて
手に負えないくらい
傷だらけとなり
僕の姿を
少しも映し出さなくなった頃
あこがれていた景色は
いよいよ僕からは
見えないものになるのだろうか
欠片(かけら)
たくさんの いただきものを 寄せ木細工のように 組み合わせて 私の全体ができている 一つ一つの欠片を どなたからいただいたものか 見分けようにも まるでお手上げの だらしない 始末だけれど
宛名書き
年賀状の宛名書きを パソコンで手伝ってやるのは ここ数年の私の習い 昨年の住所録を印刷して 母に渡してやると 一年前に頂いたお賀状の束と ひとしきり時間をかけて 照らし合わせている しばらくすると 私の部屋にやって来て 出す人とそうでない人 小さな印でよりわけた住所録を 遠慮がちに私に差し出す 私が受け取ろうとのぞき込むと 「この先生、死んじゃった いい先生だったのに」 指先で一つの名を押さえてつぶやくと 母は急に涙ぐんで それなり逃げるように 背中を丸めて部屋を出ていく 乙女なりし母の 涙をすすりあげる声が なおも静かに聞こえつづける
ここ
今 ここに いること やがて ここから いなくなること この二つは 初めから交わされている 太陽と月との 動かせない約束だ だからこそ ここにいるうちに やった方がいいことの 全部をやっておくとしよう ここからいなくなる前に 自分のありったけを 傾けておくとしよう そうすれば 僕らは きっと たくましく前へ 進んで行けることだろう ここにいた ひたむきな自分を かけがえのない 宝物として
山茶花
冬 真っ直ぐに続く 一本の道を歩み疲れて そろそろ気の遠くなりそうな心に 傍らの山茶花の花が ほうと灯を灯す なぜ こんな季節を選んで 花を咲かせるのだろうと ちょっと勇気みたいなものが ほうと灯を灯す
壊れた独楽
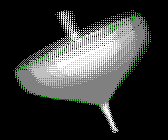
壊 れ た独楽でもそれなりに回る なんだか自分が回っている ようでこんなものさえ 捨てられない で い る

古びた小箱
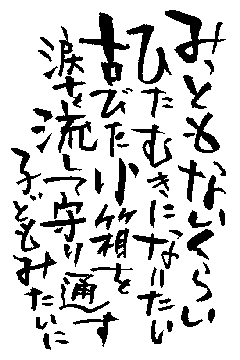
みっともないくらい ひたむきになりたい 古びた小箱を 涙を流して守り通す 子どもみたいに
まずまず
まずまずだ
何ということのない
僕の人生のことだけど
一人僕だけは
見捨てないでいこうと思う
一人僕だけが
思うようにならないというのでも
なさそうに思われるから
無題
生涯の 思い出は さりげなく ここにある ものだ
ロミオとジュリエット
ジュリエットは
ロミオがロミオであることを
どうしてと問い
家を捨て
名を捨ててくださいと
願った
互いの運命が
不幸な前提のもとに始まったことを
その時すでに知っていたからだ
僕は僕で
自分が自分であることに
どうしてと問うたことこそあったが
あなたが
今のあなたであることほど
僕には深刻ではなかったのだ
僕たちはだれしも
ようやく出会うその前に
それぞれの前提を身にまとい
簡単ではない存在になっている
生きているだけ
たくさんの鎖につながれ
予め決まったその長さの限り
僕たちは呑気でいられる
そこへやってきて
恋ってやつは理不尽だ
人が油断している隙に
何もかもお構いなしで
あらゆる鎖を
引きちぎろうと暴れ出すのだ
手に負えない勢いで
僕の中で暴れ回り
純粋に存在することを
僕に求める
呑気に飼い慣らされてきた僕は
自分にかけられた鎖を
見つめ直し
握りしめて
そのまんま立ちすくみ
途方に暮れる
真実と嘘と自分が
わからなくなる