うーわん と吠えやがる あの家の犬に 今日こそは仕返しに うーわん と吠えてやろう そうだ ついでに姪の由佳にも うーわん と吠えてやろう そうして あの家の犬に仕返しに うーわん と吠えてやったことをじまんしよう 「すごいだろ」ってじまんしてやろう
今
夕焼け雲の赤く染まったつかの間 ひまわりに風がそよぎ その背丈とちょうど同じくらいの少年が そばで葉の手招きに会って立ちすくんでいる 夕焼けのほんのつかの間 風に乗ってどんどん雲は流れ その向こうの空は明るい水色に 光っている 雲の厚みは絶望的であり その下の真っ赤な色が 少年に告げる ほら 今こそ 今なんだと
みみずの死
どくだみの花が咲く 初夏のベッドで 僕は気ままに生きていた そこが 僕の全ての生涯の在り処 それでよく それでしかなく 土の臭いはそのまんま僕の 生と死を抱く 優しい場所であったのだ どこに行こうという望みも ありはしないし 今までだって持ちはしなかった 十分な安穏に 時たま寝返りを打つことくらいが 僕の仕事で そのままいることにだけ 僕の生活は終始するはず それでよかった 遠くで かあかあかあかあ かあかあかあかあ 鳴く鳥も 僕は一度も見たことはないが それはそれで 別にどうでもいいことだった あたたかい 黒い土に 僕は愛されていると思っていたからだ 愛していたからだったろう そうだったろうと思うのだ なのに 突然だ 僕は子供の持つ棒きれにひっかけられ 落とされてはまたひっかけられ かたくて熱く焼けた日向のコンクリートの上に運ばれ のた打ちまわり あえぎ 見たこともないその場所でいたぶられ 孤独の中で絶望し ひからびていく自分を どうすることも できないまんまひからびていった 見たこともない光という光が 青い色のどんどん濃くなっていく空が 僕の目には映っていた 僕はその時ふと ああ これが死というものなのかと はじめてわかった
秋の夕暮れ
金木犀の花の 潔い真剣さに後ろめたくて 宇宙がすすり泣いている けれん味のない沈黙がやがて ため息になりはしまいかと ついと悲しんでしまう 僕の習性 おびえにも似ている 僕などは まだまだいい方なのだと しきりに心で呟くと なんだなんだなんだ 何がいいんだかちっともわかりゃしない そう思いながら少しは慰む 秋の夕暮れ
地鳴り
眠気によっても 僕の宇宙への思いは何も 何ひとつも変わらず深刻なのだ 間もなく意識は薄れながら 今日の雑多ながらくたを遥か 向こうの山陰に埋め葬ろうとしている そうして僕の世界はまぶたの中で ようやく色彩を取り戻し始め 最大級の意味を与えられるはずなのだ それなのにどうだ やっぱり駄目だ 僕の宇宙への思いは何も 何ひとつも変わらず深刻なのだ がらくたどもが あるいは 存在を主張するその叫びか 地鳴りが止まない 地鳴りが止まない 地鳴りが止まない そのせいなのだ
黄色の光
看板が斜めになり くすんだペイントの中にある黄色の 妙に鮮やかな光を放っているのが 実は君であるということを 僕はとうとう告げることなしに 今日まで時間を終えてきてしまった そうしてブリキの看板を きちんと立て直す術も持たず それでも黄色い光のところから 目を離せないまま ぼんやり見守り続け ほうりゃとばかりに 時たま思い出して自分の ずいぶんと色あせた情熱のかけらをちぎっては ばおんと看板にぶつけてみるのだ 心なしか 看板がまた斜めになる 光は一層鮮やかだが
晩夏
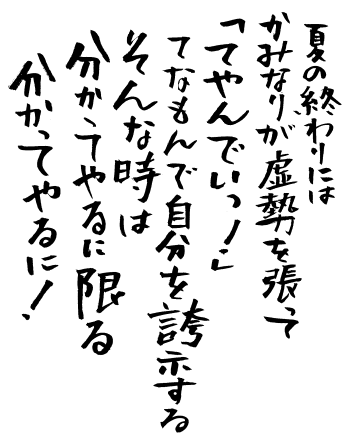
夏の終わりには かみなりが虚勢を張って 「てやんでいっ!」 てなもんで自分を誇示する そんな時は 分かってやるに限る 分かってやるに!
夏
明るい蜃気楼がそっと遠のき ふと我に返ると 人々はその傍らに ほこりと蜘蛛の巣とかびの領分と化した 古臭いあばら屋を見出だすであろう まもなく それが自らの帰るべき住み処であったことを どこか見覚えのある調度から認めねばならないであろう 同時にそうすることの空しさをわかりながら きっと呟くであろう 《まさか こんな はずでは》 人々はそして もしや長い長い魔法にかかっていたのかしらと やっとのことで思い至るであろう だれかにささやかれた 忌まわしいまじないの言葉が そう言えば と思われてくるであろう やがて柔らかな愁いが 心の中にはびこって 無数の蜘蛛の巣のように きれいに幾何学模様を作っているのを もはや諦めた顔つきで ぼんやりと眺めるであろう もちろんそれは これまでの時間を鮮やかに記念して 静かにきらきらとか細く揺れて 静かな光を放ち続けるであろう
亡命
彼の瞳に映る世界は
未来へと確かに漸進しているはずなのだ
ファシズムに立ち向かう
彼の精神は恐ろしく崇高いではないか
亡命を決意するまでの過程を今
つぶさに振り返ろうとも
その叫びも沈黙も捧げた自己犠牲も
全ては正義への願いに裏付けられていた
〈だからこそ余計 彼はその瞑眩に
自らの全体さえ見えなくなるのだ〉
もちろん
彼は失うことを選んだ者だ
愛すべき祖国を
愛すべき人々を
自らの国籍を
全てを
理想を希求する在り方までも
失わねばならなかったのだ
こうするより他に
彼の生きられる方法はなかったのだ
〈体制に反旗を翻した者は時に
信ずる正義のために死を選び
殺されることをも誇りにする〉
しかし
彼は生きたかったのだ
自分を生かそうと思ったのだ
犬死にではならなかったのだ
彼は理想を守りたかったのだ
彼の死はそのまま彼の
孤高なる精神の消滅を意味する
それだけは
彼には耐えがたいことだったのだ
あってはならないことだったのだ
〈そして 彼は 亡命した〉
だがすぐに彼は
その皮肉を思い知らねばならない
たとえファシズムに染まり切っていても
それは彼の祖国であった
たとえファシズムを信奉する者でも
それは彼の同胞たちであったのだ
憎むものも
愛するものも
彼には一つしかなかったのだ
〈亡命より他に 選ぶべき道は なかったではないか〉
そう呟く刹那
彼はまた
自分を苛み始める
〈たとえ 殺されようとも どうして
最後まで 抗い通さなかったのか〉
時間も空間も
もはや彼の味方ではない
彼はかたく歯をくいしばり
じっと思い詰めるだけだ
彼の苦悩が
愚かな失敗によるものではなく
譲れない成功の結果だからだ
仕事
雨のようなもので
どっちみちなるようにしかならないのだが
てるてる坊主を作ったり
雨乞いの神事をしたり
ずいぶん熱心にやってみたりするのだから
それも大真面目で
やってらんないくらい胸が痛むんだ
自分の仕事の意義を
何とか見つけ出さないじゃいられなくて
人間てけなげだ
俺らもけなげだ
けなげだけれど
やってらんないくらい胸が痛むんだ