みっともないくらい ひたむきになりたい 古びた小箱を 涙を流して守り通す 子どもみたいに
古びた小箱
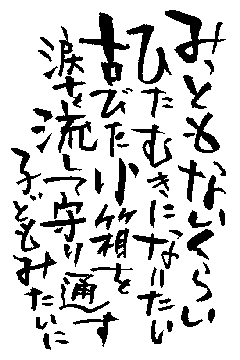
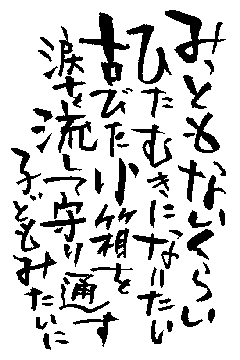
みっともないくらい ひたむきになりたい 古びた小箱を 涙を流して守り通す 子どもみたいに
まずまずだ
何ということのない
僕の人生のことだけど
一人僕だけは
見捨てないでいこうと思う
一人僕だけが
思うようにならないというのでも
なさそうに思われるから
生涯の 思い出は さりげなく ここにある ものだ
ジュリエットは
ロミオがロミオであることを
どうしてと問い
家を捨て
名を捨ててくださいと
願った
互いの運命が
不幸な前提のもとに始まったことを
その時すでに知っていたからだ
僕は僕で
自分が自分であることに
どうしてと問うたことこそあったが
あなたが
今のあなたであることほど
僕には深刻ではなかったのだ
僕たちはだれしも
ようやく出会うその前に
それぞれの前提を身にまとい
簡単ではない存在になっている
生きているだけ
たくさんの鎖につながれ
予め決まったその長さの限り
僕たちは呑気でいられる
そこへやってきて
恋ってやつは理不尽だ
人が油断している隙に
何もかもお構いなしで
あらゆる鎖を
引きちぎろうと暴れ出すのだ
手に負えない勢いで
僕の中で暴れ回り
純粋に存在することを
僕に求める
呑気に飼い慣らされてきた僕は
自分にかけられた鎖を
見つめ直し
握りしめて
そのまんま立ちすくみ
途方に暮れる
真実と嘘と自分が
わからなくなる
旧道のトンネルの中は
いつも暗く
ひんやりとしている
まるで永遠のような
その静寂の中を
ひときわ冷たい水の
雫の落ちる音が
響くとき
響くとき
少しだけ
時間の流れがひずんで
後戻りするんだが
後戻りするんだが
捧げられた「祈り」の分だけ
人々の生涯は
確かに幸せになって
きたのだろうか
信仰というものが
ろくにないんだから仕方も無いが
僕の場合にはどうにも
祈りという祈りが
いつもいつも
無力だった気もする
祈りというのは
限界にまで至ったときの
無意識の呟き
のことかしら
全力の果てに絶望がつくりだす
まじないのことば
のことかしら
言葉にもならぬまま昇華する
涙の結晶を天に送る
自然のしぐさ
のことかしら
いずれにしても
僕のはどうにも
効き目がないんだ
水平線がまあるく どうやったら見えるんだろう まだ本当には そう見えたおぼえがないんだ ないしょだけど
「奈津子は初めからいなかった」 そう言っても 何も差し支えはないんだが…… 子供らに人生なんかを説いて 僕の人生が終わってゆく 終わってゆく 馬鹿げちゃいるが もしもの話 誕生したその時 終わっていたと仮定したら 僕という存在は どこへ向かって行ったのだろうか 奈津子の遺影が 仏壇の中から 前触れなく消えた そういう日があった 古びた小さな木の額ごと 白黒写真が消えていた 確か 僕が高校生だった頃だ その子のために用意された 白い産着に包まれて眠る 奈津子という名の 赤ん坊の写真が消えた (奈津子というのは 僕の姉として存在したはずの 一度も存在しなかった人の名だ) 僕はそのまま 取り立てて聞こうとも しなかった そのまま 奈津子の写真が戻らない それならそれで きっといいのだと思ったからだ 僕の人生が 今 あるように 奈津子の人生は あるはずだったろう 父や 母の 人生があるように 奈津子の人生は あるはずだったろう 僕は小さいときから 姉さんが 確かにいるような気でいたんだ 馬鹿げちゃいるが 僕の人生と一緒に(僕だけじゃない?) 奈津子の人生はあったのだ ……そういう気もする 今だから言えるんだが
世界中に毎日 絶滅している生物が たくさんあると聞くが その終わりはきっと 人知れず あっけないものなのだろう 終わってみれば 結構あっけないものなのだろう 終わったんだか 何だか よく分からないような ささいな 出来事なのだろう 亜熱帯の森林が伐採され 地球のオゾン層が破壊され 物言わぬ海に 最後のツケは回され 人間の横暴を責めてみるのも 何だか絶望的に思われるばかり 今さら原因が何かと 問い直してみたところで たいした手だては見つからない みんな 自分のことだけで 精一杯なのだから 「たぶん それでいいんだよねえ」 そんなふうに 大概のものは 結構あっけなく終わるものなのだから 人の人生が 終わるときであっても そしてたぶん 人の歴史が 終わるときであっても 「たぶん それでいいんだよねえ」 いいわけないじゃないか! と だれでも口を揃えて言いはするだろうが
霙の中を 卒園式帰りの母子が 傘をさして通り過ぎます 着飾った若いお母さんは 子供の制服の胸にあるリボンと ちょうど同じようなピンクの きれいなスーツを着ているのです 冷たい霙は 傘の上にもうっすら積もって 子供の黄色い傘には ちょっと重たそうに思われるのですが どうやらへっちゃらみたいに ぜんぜんお構いなしに 子供は飛び回って歩くのです 茶色い雨傘の中で それを微笑ましく眺めながら だれが立ち止まってみても 何者も気付きはしない! そういう春の昼下がり 冷たい霙は 一向に降り止みません 冷たい霙は 私の上にも積もっているのかと そうやって思い至ってみると それは何だか結構うっとうしく やけに重たく 道端でふと 何だか泣きたいような気分になって けれどまた もう一度歩きだすより他に 私にはなかったのです